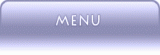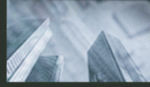�@�_�炩���Z�p
�@�P�D�_�炩���Z�p�Ƃ�
�@�}�Y���[�̂����Љ�I�~���̎���ɂ����鍂�x�������܂ł́A�����Ƀ��m�s���̎���ł��������B�������A�s��͗ʎY�̐��ɂ��ƂÂ��}�X�E�}�[�P�b�g�ł������B�����ď��i�i���i�j�́A�Z�p�v�V�ɂ��@�\�E���\��D�悵���v���_�N�g�A�E�g�^�̊��E�J�����Ȃ���Ă����B
�@���������l���E�����̎���ɓ���A���E�J���̃A�v���[�`�Ɂu�R�g�v����̔��z���]�܂��悤�ɂȂ�A�]���̃A�v���[�`���@�\�E���\����̂Ƃ����]���̉�������̊��ł������̂ɑ��A�R�g�i�\�t�g�I�Z�p���_�炩���Z�p�j�����ڂ𗁂тĂ���B�܂�A�_�炩���Z�p�Ƃ̓}�[�P�b�g�C���̔��z�Ŋ��E�J������Z�p�ł���Ƃ�����B
�@���m�Â���̏o���_�́A����ҁi�Ƃ������ނ��됶���ҁj�̂��u�j�[�Y��E�H���c�v�̔�������͂��߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����āA���m�ɂ͐����̕����i�R���e���c�j�̊�ՂƂ��āA�����ɖ����ւ̐V���������̎������R�g�Ƃ��Ċ܂܂�Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���������o�����Ƃ����z�ł���A���̂��߂̐G�}�����g���b�N�u�A�i���W�[�v�I�v�l�Ƃ�����B
�@
�@�Q�D���z��L�ɂ��邽�߂�
�@���z�Ƃ́A���̐l�̒m���ƌo���Ɋ�Â��ĂȂ����B���Ƃ��ƒ~���Ă���m���ȏ�ɔ��z�͏o�Ȃ��B���ꂪ�Œ�ϔO�ƂȂ��Ĕ��z��݂点�Ă��܂��B�ł͌Œ�ϔO�����Ă�Δ��z�͖L�ɂȂ�̂ł��낤���B����������͖����Șb�Ȃ̂ł��낤�B�Ȃ��Ȃ�A�Œ�ϔO�����Ă�Ƃ������Ƃ́A����܂ł̐l����ے肷�邱�Ƃɂق��Ȃ�Ȃ�����ł���B
�@���z�́A��l�̎v�l�̘g�g�݂ł͌��E������Ƃ������Ƃ��킩�����B�����l����Ε����ōl����Ηǂ����Ƃ������ł���B���̂��߂ɂ́A���l�Ƃ̌��t�̃L���b�`�{�[�����s�����Ƃ��K�v�ł���B��������ʓI�ɍs�����߂̃c�[����Z�@���������l�����Ă���B
�@�����锭�z���g�U������h���Ƃ��Ă̋Z�@�ɂ͓����B��Ԗڂ͎����̔��z�ɂ����̃X�N���[���������I�ɂ�������@�ł���B��̓I�ɂ̓`�F�b�N���X�g�@�ł���A��������������o����Ă���B��Ԗڂ́A���l�َ̈��������Z�@�ł���A��\��Ƃ��Ă̓u���C���X�g�[�~���O�@������B
�@���ӂ��ׂ��́A���z�@�͒m���ƌo�����ǂ��g�����Ȃ����Ƃ����G�}�ł����āA���z���Ƃ���Ăɉ��o���Ă����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�Z�@���A���ꂪ����Δ��z�ł���ƍl����̂ł͂Ȃ��A�������g���h������A�����̒��̔������菕������A���z�̂��߂̏��̈�ƌ��Ȃ��ׂ��ł���B
�@��Ԃ�ł͔��z�͂ł��Ȃ��B���z�ɂ͖ړI���K�v�ł���B�����ĖړI��B�����邽�߂ɂ͉����𗧂ĂȂ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ���m�ɂȂ�A���p���ׂ��Z�@���i�荞�܂�A�����l�Ƃ̃L���b�`�{�[�������₷���Ȃ�B�u�j�[�Y��E�H���c�v�͂����������z�v���Z�X��ʂ��Ĕ�������A�����ď��i�i���i�j�Ƃ��ċ������Ă����B
�@
�@�R�D�m�������q�b
�@����܂ł̓��{�̋���ł́A�u�����v���o�����Ƃ��������Ă����B���̂��ߔ��z�ɂ����Ă����������߂悤�Ƃ������ł���B���������z�͒m���ł͂Ȃ��̂ŁA����܂ł̐ςݏd�˂���͐��܂�Ă��Ȃ����A��̐���������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B
�@����Ȃ̂ɁA�m���ɗ��������z�@����肪���ƂȂ�B�m���Ȃ�w�ׂΎ�ɓ������B�m���Ă���l�ɕ����Β�����ɓ���B���邢�́A��B���K���ǂ����ɂ���Ƃ������Ƃł���B�������A���z�ɂƂ��ẮA�m����Γ���قǁA�t�ɕs���R�ɂȂ肩�˂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A����͂��̂܂܁A�u�����ł͂����Ȃ��Ă��Ȃ��v�u�����ł͂�������Ă���v�Ƃ����A���z��~�̍ޗ��ɂȂ邾���ł��낤�B
�@�V���Ȗ��̉����A����̉��v�A���Ԃ̑ŊJ�A�s���l�܂�̑Ŕj�A��ւ̃u���C�N�X���[���X�̂��߂ɂ́A����܂ł̒m����o���̉�������ł��Ȃ��A���܂̂܂܂̂����ł��Ȃ��A���܂܂ł̏펯�ɂƂ��ꂸ�A�V���Ȕ��z�Ǝv�l�̘g�g�݂�n��o���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@���z�́A��������̂ɂ��킹��̂ł͂Ȃ��A�������悤�ɕς��Ă��܂��A�������悤�ɁA���邢�͌�����悤�ɕς��Ă��܂����Ƃł��낤�B���z�́A�Z�@���g�����Ȃ��Ƃ����݂̂ł͐��܂�Ă��Ȃ����Ƃ��̂ɖ��������B
�@�H�i�I�j���x������̂Â���
���֒q�O���̍u��������������@�����܂����B���͒��H���50�N�̐��ՍH�����𑗂�Ȃ���A�������̒������o����Ă���E�l��Ƃł��B
���ۂɁA�؍킵�Ȃ��ň����@�����Ő��������A�J�����ɓ�������钴���g���[�^�̎厲�i���������쏊�j�A�v���X�����ɂ��ʋl�p�_�u���Z�[�t�e�B�E�v���g�b�v�i�J�[���쏊�j�A�p�C�v���Ȃ��Đ��������G���{�A�G�A�]�[���g�p��ɍŌ�܂ŃK�X��������H�v�̊W�Ȃǂ̃T���v����q�����܂����B
����炻�̂��̂́A�т����肷��悤�Ȏa�V�ȃ��m�ł͂���܂��A�����@�E�菇�i�v���Z�X�j��ς������ƁA�����ɒ~�ς��ꂽ�Z�\�����p�������ƂȂǁA�E�l�̒m�b�ƍH�v���W��Ă��܂��B
���̂Â���̍H�i�����݁��I�j�̉��[�����Ђ��Ђ��Ɠ`����Ă����u�����e�Ɋ������A���̌㉽�����̒�����q�ǂ��܂����B�����ɂ͂��̂Â�������������A�ȉ��̃��b�Z�[�W���Ïk����Ă��܂����B
�@����͊������m�b�̕�ɂł���B�m�b������������ǂ�ȗD�ꂽ�@�B�������Ă��A�D�ꂽ���\�̐��i�͍��Ȃ��B
�A�@�B�͐l�̐S���ʂ��B��������߂��A���x�A�������l�����A�����ʎY�݂̂��u������̂ł́A�~�N�����I�[�_�[�̐��x�͈��肵�ďo���Ȃ��B
�B�K�i�ɂ͊O��Ă��Ȃ����A����Ȃ��̂��o������H��̒p���Ƃ���l�̍�郂�m�́A���������Ⴄ�̂ł���������B���̂Â��肪�z���Ă������l�ςł���B
�C�R���s���[�^�t�̋@�B���o�͂��߂�����́A�n���s�v�̎��オ����Ă����Ƃ���ꂽ�B���������Չ��H�͘c�Ƃ̐킢�B�n���Ƃ͂����\�����Ď̂Ă�H�v�����邱�Ƃł���B
�D���͒m�b�̂����܂�B���݂͂�Ȏ̂Ă�H�v�B�R���s���[�^�Ɏ̂Ă�Ƃ����v�z�͂Ȃ��B�n���̑������̂Ă�Ƃ������t�Ŋ���邱�ƂɋC�Â����B
�E�E�l�Ƃ̓��m����铹�i�v���Z�X�j���l���A���m����铹��i���j���H�v���邱�Ƃ̂ł���l�Ԃł���B
�����̓��e����A�R���T���^���g�Ƃ��čl����ׂ�������������ɂȂ�܂��B
��ڂ́A���̂Â���̉��l���ĔF�����邱�Ƃł��B���̂Â���́A�g�M�����̍������m�����肵�Ă������������h���Ƃ��ړI�ł��B���������̎��g�ݎp���̏��Ԃ��d�v�ŁA�g�����h���ŏ��ɗ��Ă͗ǂ����m�͂ł��܂���B
���̂���ւ́A�m�b�ƍH�v�̊��p�ƒ~�ς𐄐i���邱�Ƃ���ŁA���̂��߂ɂ̓��m�����l�����̎Љ�I�n�ʂ����߂�K�v������܂��B���m���J�l�ɂ������Z�ł��Ȃ��Љ�́A���̂���̌��ꂪ�y���镗���݂܂��B���m�́g���h��������������g�ɕt����ׂ��ł��傤�B
��ڂ́A�R���T���Ƃ��Ẵv���Z�X�������Ƃł��B���̂Â���̋Ɩ����P�̎x�������߂�ꂽ�ꍇ�A�S�̂����Ď菇�i�v���Z�X�j���C���[�W���邱�Ƃ���ł��B
����ɂƂ��đ�Ȃ��Ƃ́A�ۑ�ɒ��ڃA�v���[�`����Ƃ����ߎ���I�ȑΉ��ł͂Ȃ��A���i�Ƃ��Ăǂ̂悤�Ȃ��̂���肽���̂��A���̂��߂̍H�v�̗]�n�͂ǂ��ɂ��邩�ȂǁA�����߂�v���Z�X��^���Ă���邱�Ƃɂ���܂��B

|
�@�헪�I�ӎv����
�헪�I�ӎv����Ƃ�
�헪�I�ӎv����͌o�c�̖{���I�����ɂ̋@�\�ł���A�����E�挩���E�n���I�v�V�́E���́E�_�͂Ȃǂ������ߍ��ȉۑ�ł���B���̂����́u�헪�I�v�Ƃ́A��肪���邩�ǂ����s���ȏɂ����Ė������o���A������������邱�Ƃł���B�܂�u�������₢�v�����o�����Ƃ������B
����ɑ��āA�^����ꂽ���ɑ��āu�����������v���o�����Ƃ͐�p�I�Ƃ�����B�i�w�������₢���킩�炸�ɁA������������������͂����Ȃ��xP.F.�h���b�J�[�u����̌o�c�v���j
�헪�I�ӎv����̗v���͎��̂悤�ɂ܂Ƃ߂���B
�@�E��������v���邽�߂̖����`������
�@�E�����I�Ɋ�Ƃ̑��S�����E����
�@�E�s�������B���ȏɂ����ă��X�N�e�C�L���O����
�@�E�o�c�N�w��M�O�����f�����
�A�T�q�r�[���̎���
���ł����A�T�q�r�[���̓r�[���ƊE�̃g�b�v�̍����L�����ƕ��������Ă���́A�ꎞ�͎s��V�F�A��10�����܂łɗ��������A2001�N�ɂ̓r�[���E���A���o�חʂŎs��V�F�A��38.9�����߁A�g�b�v�𑱂��Ă����L�����r�[����35.8��������A�g�b�v��D���Ԃ����j�I�ȕ��������������B
���̌����ȕ��������w�������o�c�҂̃��[�_�[�V�b�v�ƈӎv����ɂ́A�w�Ԃׂ��Ƃ��낪�����B�����1�l�̃J���X�}�I�o�c�҂̐�����Z�ł͂Ȃ��A��������Г��̈ӎ����v���s���ĕ����̎�������A��������L���Y�����p���ŕc����āA���˗Y�O�����傫���ԊJ�������Ƃ����A�R��ɂ킽��В��̋��͂ȃ��[�_�[�V�b�v�̔����ƈӎv����̃R���r�l�[�V�����́A�v�V�I�Ȏ���ł��낤�B
��������̎���i1982�`86�N�j
�g�b�v�哱�̑g�D�v�V�����s�B�o�c���O�E�s���K�͂����肵�A��ƕ��y�̉��v�Ɏ��g�݁ACI�i�R�[�|���[�g�A�C�f���e�B�e�B�[�j���B�^�u�[������Ă����u�r�[���̖���ς��v�A�R�N������̂ɃL�������鐶�r�[���̔����ɑ����������B
������L���Y���̎���i1986�`92�N�j
���䎁�̖����ϋɘH����W�J�B����ȃ��[�_�[�V�b�v�����āA�g�b�v�_�E���ɂ��ӎv��������{�B�H��̗��v�Ǘ����x��p�~���A�u�H��͏��i�Â���ɓO����A��Ђ̃}�l�W�����g�͌o�c�҂ɁA���v�ӔC�͎В��ɔC���Ă��������v�ƐӔC�̏��݂m�ɂ����B�K�v�ȋ��͐ɂ��܂Ȃ��o�c�B�X�[�p�[�h���C�̊�Ղ����o�B
�����˗Y�O���̎���i1992�`99�N�j
���������Ō���p���A�N�x�̋S�Ƃ��ĎГ��̃��Y���Ƌْ�����ۂ{���łB�u�U�߂̌o�c�v����u�o�����X�o�c�v�ցB�H��o�ׂ܂ł̊��Ԃ��B�V�F�A�t�]���ʂ�������No.1�̍����ˎ~�߂������ҁB
�ӎv����̓���
�O���̌o�c�҂Ƃ��Ă̊������e�ɂ͓��R�Ȃ��瑊�Ⴊ���邪�A���̈ӎv����v���Z�X��[�_�[�V�b�v�X�^�C���ɂ͉��L�̂悤�ȗގ��_��������B
�@�ӎv����v���Z�X
���ׂ����e���Ɏ����g�b�v�_�E���I�ł͂��邪�A�����Ȃ�̎w���ł͂Ȃ��A�헪�r�W�����������Ă܂��Ј��ɓ��e���\���ɝ��܂��āA���̌��ʂ���������āu�ӎv����̏�v�Ƃ��Ă̎��������������B�Ō�Ɏ��炪�ӎv���肷��Ƃ����v���Z�X��������B
�P�Ɋe���傩�瑽�i�K�̍��ӌ`�����o�Ă����オ���ė����Č����A�ŏI�I�ɏW�c���c���ɂ���Ĉӎv���肷��{�g���A�b�v�������Ƃ��Ă͂��Ȃ��B
�A�ӎv������e
�悪����������Ă݂Ȃ���킩��Ȃ����A�����s����Ɩ����Ƃ����؉H�l�������ŁA�u�O�Ⴊ�Ȃ��A��������v�i��������j��M���Ƃ����A��_�������Ȉӎv������s���Ă���B�܂�A�ߋ��̐����o���⌻��̉�������Ŕ��z��������A���邢�͎Г��̗��Q�W�f�����Ë��I����ł͂Ȃ��B
�B���[�_�[�V�b�v�X�^�C��
������e�̔F����O��m�ɂ��A�Ј��̋����邱�ƂŁA�Q��ӎ������߂Ă��C�������o�����ƂɎ���u�����B�܂�����̂��Ƃ�ǂ��m�邱�Ƃɕ��S�����B�e�l���{�������Ă���\�͂�������Ƃ����A�x���I�s���������w���I�s�����Ⴂ�A�u�x���^���[�_�[�V�b�v�X�^�C���v������Ă����ƌ��邱�Ƃ��ł���B
���Ⴉ��̒m��
�헪�I�ӎv����̗̈�́A���ƕϊv�E�V�K���Ɛi�o�A�l���`�A�ӎ��ϊv�A�g�D���v�ȂǑ���ɋy�ԁB�n�Ƃ͖{���헪�I�v�f���v���ł���̂ŁA�n�ƌo�c�҂ɂ͐헪�I�ӎv����̎�������o���₷���B
�t�@�[�X�g���e�[�����O�A�}�N�h�i���h�A�z���_�A�\�j�[�Ȃǂ̑n�Ǝ҂̈ӎv���莖�Ⴉ��́A�J���X�}�I���[�_�[�V�b�v���w�Ԃ��Ƃ��ł���B
�����������̐��o�c�ҁi�T�����[�}���o�c�ҁj�͔����̏�Ɏ���̍\�}��`������ɂ͂Ȃ��̂ŁA�]���H���������p���Ń��X�N���������s��ׂ̍߂�掂��Ƃ�Ȃ�������U������邪�A�A�T�q�r�[�����n�߂Ƃ��Ē�������Ƃ�h�点���u�����̑c�v�Ƃ������o�c�҂������B���̍Č��ߒ��ł̐헪�I�ӎv����ƃ��[�_�[�V�b�v�X�^�C���͊w�Ԃׂ��_�������B

|
�@�T�v���C�`�F�[���}�l�W�����g(�r�b�l)�čl
�͂��߂�
�T�v���C�`�F�[���\�z�̖ړI�́A�Ɩ������v���Č��������シ�邱�Ƃ͂������̂��ƁA�R���{���[�V�����ɂ���Ɖ��l�̌���A����ɂ͂��炽�ȃr�W�l�X���f���W�J�ւ̉\���܂ł����܂�ł���B
�����̊�ƂŃT�v���C�`�F�[���\�z���i��ł���A������g�傷��@�^�ɂ���B�T�v���C�`�F�[�����œK�ɕۂɂ́A��Ɠ��O��ʂ����S�̍œK��ڎw�����^�p���K�v�ł���A���̂��߂ɂ͖ړI�Ɖۑ���\���ɔF��������ł̐��i���K�{�ƂȂ�B�{���|�[�g�ł͂���痯�ӓ_�ɂ��Ę_����B���ł�SCM���i��̉ۑ�ɂ��Ă̍l�@�𒆐S�Ƃ���
�O���[�o���T�v���C�`�F�[���Ƃ�
�i�P�j�T�v���C�`�F�[���Ƃ�
�|�[�^�[(*1)�́A��Ɠ����̊����݂͌��ɘA���W��L���A�S�̂Ƃ��Ĕ�����̂��߂̉��l��n�����Ă���A���̘A���W�����܂��Ǘ����邱�Ƃ��ł���A�����D�ʂɗ��Ă�Ǝw�E����B�܂�A�����D�ʂ��l������ɂ́A��Ƃ̃o�����[�`�F�[�����X�̕����̏W���Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�ЂƂ̃V�X�e���Ƃ��ĊǗ�����K�v������Ǝ咣����B���ꂩ��A��Ɠ��̕�����я��̗�����o�����[�`�F�[���ƌĂ�ł��邱�Ƃ��m�F�ł���B
����A�T�v���C���[����ڋq�Ɏ���܂ł́A��Ƃ����f�������i�A�T�[�r�X�A����ъ֘A���̗�����T�v���C�`�F�[���ƌĂсA���̗�����œK�����ĉ��l�傳����r�W�l�X�헪���T�v���C�`�F�[���}�l�W�����g(SCM�FSupply Chain Management) �Ƃ����B
�Ȃ��A�O�҂̃o�����[�`�F�[������Ɠ��T�v���C�`�F�[���ƌĂсA����ɑΉ�������`�ŃT�v���C���[����ڋq�Ɏ���܂ł̊�Ƃ����f�����T�v���C�`�F�[�����A��ƊԃT�v���C�`�F�[���ƌĂԃP�[�X��������B
SCM�́A���i�ƃT�[�r�X�ɑ���s��̎��v�ݏo���Ă���������܂��܂ȃv���Z�X����\�������B����́A�ŏI�I�Ȍڋq��������Ƃ������ʂ̖ڕW�Ɍg����Ă������p�[�g�i�[�E�R�~���j�e�B�S�̂������A�̃r�W�l�X�E�v���Z�X�̏W���ł���B���������āA�T�v���C���[�̃T�v���C���[����ڋq�̌ڋq�܂ł�ΏۂƂ���K�v������B
����p�[�g�i�[�E�R�~���j�e�B�������ɗ��܂炸�A�����܂�����SCM���O���[�o��SCM�iGSCM�j�ƌĂԁB
�i�Q�j�O���[�o���Ƃ�
�O���[�o�����ƍ��ۉ��Ƃ͈�����u���Ă���B���o�[�g�E���C�V���́w�U�E���[�N�E�I�u�E�l�C�V�����Y�x�ŁA�u���̐��I�̐����E�o�ςł́A�����̐��i�Ƃ��Z�p�͑��݂����A�����̊�ƁA�H�ƁA�o�ς����݂��Ȃ��B����̃O���[�o���o�ώЉ�猩���Ƃ��A�����͈Ӗ��͂Ȃ��v�Ƃ��Ă���A�O���[�o�����̖{���̈Ӗ��́A�{�[�_�[���X�܂荑�����ӎ����Ȃ��Ƃ������Ƃł���B����̍��ۉ��́A�u���v�́u�ہv������A�������ӎ�����Ă��邱�Ƃ������B
�����������ꍇ�͌��R�Ƃ��č��������݂��A������ӎ������������K�{�ƂȂ�B���̈Ӗ��ł́A�����ň��������܂�����SCM�͍���SCM�ƌĂԂق��������������A�吨�Ƃ��ẴO���[�o��SCM�ƌĂԂ��ƂƂ���B
���̃O���[�o��SCM�́A�����j�[�Y�ɉ����邽�߂ɐ��E�I����ɂ����čł����_�̂���n��ɃA�N�Z�X���邱�ƁA�܂�œK�s��A�œK�n�w���A�œK�n���Y���w�����邱�Ƃł���B
�i�R�j���W�X�e�B�b�N�X�Ƃ̊֘A
�T�v���[�`�F�[������ƊԂ̘A�g���d������Ƃ������Ƃ́A���̍œK���ɂ͕������傫�ȈӖ��������Ƃł���B�����̕���ł��A���̃T�v���C�`�F�[���T�O�̑䓪���āA������E���[�J�E�̔���E�ڋq�܂ł��g�[�^���ɑ������A�V�������W�X�e�B�N�X���m�����悤�Ƃ�����g�݂��Ȃ���Ă����B
���(*2)�́A�T�v���C�`�F�[���Ƃ́u���Y����̔��Ɏ���~���ȃ��m�̗���������т��č��グ�邽�߂̓��������ꂽ���W�X�e�B�N�X�E�V�X�e���̂��Ƃł���v�ƒ�`���A�T�v���C�`�F�[���Ə]���^���W�X�e�B�N�X���قȂ�_�́u�g�D�E�V�X�e���̓����A�헪���A�Ɉ��k�@�\�v�̂R�_�ł���ƕ��͂��Ă���B
�܂�A��Ɠ��ɂ����Ă͒��B����̔��Ɏ��鐶�Y�E���ʊ�����S���e�g�D�A�e���傪�A���������P��g�D�̂悤�ɘA�g���Ă���A�@�\�I�ɂ���̃V�X�e���Ƃ��ē�������Ă���B�����āu�����v���A�e�X�̃R�X�g��s��V�F�A�ɋ����e�����y�ڂ��Ƃ����헪�����A�e�g�D�A�e����ɂ����ĔF������Ă���A�����āA���̋��L��~�ς�ʂ��āA�ɒ������}����Ǝ咣���Ă���B
����ɁA��������ڋq�Ɏ���܂ł̊e��Ƃ��A�g���āA��̃V�X�e���Ƃ��ē������ꂽ�`��SCM�ł���B
�i�S�j�T�v���C�`�F�[���̎�i��
�T�v���C�`�F�[���́A���ʃ`���l���S�̍œK����ړI�Ƃ�����̂ł���A���̂��߂ɁA��ƊԂ̘A�g�̕��@�E�d�g�݂����ɂȂ邪�A�����B�������i�Ƃ��ċr���𗁂т��̂��A���̓�����A�E�g�\�[�V���O�ł���B�܂�A�T�v���C�`�F�[���́A��Ɠ�����ъ�ƊԂ̃��W�X�e�B�N�X�֘A�����̐헪�I�����ɓ���������Ƃ������Ƃ������� ���������ϓ_���琼�V(*3)�́A�T�v���C�`�F�[���́A�헪�I��g�i�X�g���e�W�b�N�E�A���C�A���X�j�̏d�v��i�ł���ƍl������Ƃ̎w�E���s���Ă���B�Ȃ��o���[�\�b�N�X�ق�(*4)�́A�u�헪�I��g�Ƃ́A�����̓Ɨ������g�D�̂����ʂȖړI�B���̂��߁A�ٖ��ɋ��͂������ӎv��������Ă���r�W�l�X�W�������v�ƒ�`���Ă���B ����(*5)�́A�헪�I��g�̖��_�Ƃ��āA�����̕s����g�D��̏�Q�Ȃǂ��w�E����B�����Đ헪�I��g�́A����A���P�I�ȁu�n��v����A����I�ŃC�R�[���E�p�[�g�i�[�V�b�v�d����悤�ȁu���a�^�������U�v�V�X�e���Ƃ��ẴT�v���C�`�F�[����ڎw���ׂ��ł���Ǝ咣���Ă���B
(*1)�|�[�^�[,M.E.�A�y�ق���w�����D�ʂ̐헪�x�_�C�������h�ЁA1985
(*2)���q�s�w�R���r�j�G���X�E�X�g�A�E�V�X�e���̊v�V���x���{�o�ϐV���ЁA1994
(*3)���V���u�����A���Ǘ��ɂ�郍�W�X�e�B�N�X�E�R�X�g�Ǘ��v�w��Ɖ�v�xVol.49,No.5�A1997
(*4)�o���[�\�b�N�X,D.J.�ق�,�F�쐭�Y�ďC�w��[���W�X�e�B�N�X�̃L�[���[�h�x�t�@���I���A1992
(*5)���ۉh�i�w���W�X�e�B�N�X�v�V�헪�x�����H�ƐV���ЁA1993
�r�b�l�E�f�r�b�l�̉ۑ�
�i�P�jSCM�\�z�̌�
SCM�\�z�ɂ������ẮA�S�̍œK�̂��߂̓��ꃂ�f���Ɋ�Â���ƊԘA�g�̕��@�E�d�g�݂����ɂȂ邱�Ƃ������ł������A����ɁA��ƌo�c�̐V���ȃr�W�l�X���f���̒T�������߂��Ă���_���w�E����Ă���B�Ƃ�킯�����Ƃɂ����ẮC�uSCM���������̂��߂ɗp����v�Ƃ������l��������C�u�V�����r�W�l�X���f��������Ă����v�Ƃ��������ւƕώ����Ă���B���Ƃ���EMS�̑䓪�̓r�W�l�X���f���̕ώ��̈�ł���B���̔w�i�Ƃ��Ċ�ƌo�c�̂��߂̃r�W�l�X���f���C�܂�u�ׂ����v���ω����Ă������Ƃ��グ����B
�Ƃ͂����A�S�̂̍œK���̂��߂ɂ͌X�̍œK�����B������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Â�����o�c�ɂ�����ӎv����̃��x�����i�X�g���e�W�b�N�j�C�����i�^�N�e�B�J���j�C�Z���i�I�y���[�V���i���j�̂R�̊K�w�ɕ����čl���Ă���̂ɂȂ炢�C�����ł�SCM�̍œK�����C�ӎv���背�x���̈Ⴂ�ɂ���đO�q�̂R�ɕ����čl����B
�i�Q�j�����i�X�g���e�W�b�N�j���x���̍œK��
�S�̍œK�̂��߂̊�ƊԘA�g�̈ӎv����͎�ɂ��̃��x���ɑ�����B�����ł̍œK���ΏۂƂ��ẮA���W�X�e�B�N�X�E�l�b�g���[�N�S�̂̍œK�v���グ����B�܂���̓I�ȍ��ڂƂ��āA
�@���W�X�e�B�b�N�X�̃t���[���i�ڋq�Q�i�N�����q�l���j�A�ݔ��z�u�i���Y���ǂ��ōs�����j�C�����z�u�i���ނ�i�̗�����ǂ������邩�j�AEMS�̗̍p�Ȃǂ��܂ށj
�A�����p���I���B�����̌���i�����I�Ȏ�����ǂ��\�z���邩�AVMI�̗̍p�Ȃǂ��܂ށj
�B���ێ���ւ̑Ή����@�̌���i�ŁC�ōT���C�ړ]���i�j
�C�s�m�����i�בցC���v�Ȃǂ́j�ւ̑Ή����@�̌���
�D���o�[�X�E���W�X�e�B�N�X�ւ̑Ή����@�̌���
�����ӎ��̍��܂�ɂ��A��������ڋq�܂łƂ��������݂̂𑨂���SCM�ɗ��܂炸�A�Ö��܂ňӎ��������o�[�X�E���W�X�e�B�N�X�ւ̑Ή��͕K�{�ƂȂ��Ă���B
�Ȃǂ��グ����B�O�q�̍ɒ����Ƃ����Ӗ��ł́A�Ώۂ̓t���[�ɂƂȂ�B
�i�R�j�����i�^�N�e�B�J���j���x���̍œK��
�S�̍œK���ɂ݂��A��ƌX�ɑS�ЂƂ��Ă̍œK����}��ӎv����͂��̃��x���ɑ�����B�֘A��Ƃ��܂߂��œK������܂���B��̓I�ȍ��ڂƂ��āA
�@���W�X�e�B�b�N�X�̃t���[�v�i���Y�E���������ǂ��ōs�����j
�A�����p���I���B�����̌���i�����̈���I�Ȓ��B�����ǂ����s���邩�j
�B�T�v���C�`�F�[���S�̂̎������p�v��i���v�̋G�ߕϓ���i�C�ϓ��̍l�������v��A���i���C�t�T�C�N�����l�������v��A���v�Ǘ����l�������v��i���i������ϐ��j�j
�C�X�g�b�N�ɂ̍œK���i�T�[�r�X���x���ێ��̂��߂̈��S�ɁA���S�ɂ̍œK�z�u�A�����̓t���[�ɂ������j
�D���b�g�T�C�Y�œK���i���S�ɁA���Y������z���j
�Ȃǂ��グ����B�ɒ����̓X�g�b�N�ɂ��ΏۂƂȂ�B
�i�S�j�Z���i�I�y���[�V���i���j���x���̍œK��
��ƌX�ɋƖ��Ƃ��Ă̍œK����}��ӎv����͂��̃��x���ɑ�����B��ʂ̈ӎv������e�Ɩ�������������ꍇ�����邪�A���̎��͏�ʂ�D�悷��B��̓I���ڂƂ��āA
�@�X�P�W���[�����O�̍œK���i�����ւ̎��Ԏ���̍�Ɣz���̍œK���A��������t���X�P�W���[�����O�A
�A���Y�̍œK���i�i���Ɛ��Y�̃g���[�h�I�t�A�W���X�g�C���^�C�����Y�A�������p���Y�A���Y���b�g�T�C�Y�j
�B���B�̍œK���i�W���X�g�C���^�C���ɑΉ��j
�C�A���E�z���œK���i�\�͂ɉ������^�p�A����p�ŏ����j
���グ����B
�i�T�jGSCM�����̓��
SCM�œK���ɂ́A����܂ŏq�ׂ��悤�ȑ����̑Ώۍ��ڂ�����A���ꂼ��ɉۑ肪�T���Ă���B������Ɠ��̍œK���ɂ��ẮA��������ђZ�����x�������S�ƂȂ肻�̕��@�_��T�|�[�g�c�[�����[�����Ă����B���_�I���Â��Ƃ��Ă�OR�ɂ��œK���A���_�A���W�X�e�B�b�N�X���_�Ȃǂ�����A��Ɠ��̌��[���̕ύX�i�Â�����̊��K�̑Ŕj�j�Ƃ����l�b�N�͂��邪�A���������͌��o���₷���B���̂��߃c�[��������O��Ƃ���SCM�\�z�Ɍ������Ă��傫�ȊԈႢ�͂Ȃ��B
��������ƊԂɍL�����ꍇ�́i�����܂����Ȃ�SCM�ł��j�A�܂������I���x���̈ӎv���肪�O��ƂȂ�A���̏�ł̒������x���ł̕��@�_��W�J���邱�ƂɂȂ�B���̂��߂̗��Â��͐헪�I��g�_�A��ƌo�c�_�A�`���l�����_�Ȃǂł���A������������ӂɋ��܂��ł͂Ȃ��B�܂��S�̍œK���f���͎���i���j�ɉ����ĕω�������̂ł���A�����̌����͂Ȃ���Ă�����̂́A�m���������f���͉Ǖ��ɂ��Č�������Ȃ��B
����ɁA�����܂����Ȃ�SCM�Ɣ�ׂāA�����܂�����GSCM�̎����͈�w�̓��������B���̗v���Ƃ��ẮA�����܂������ƂŐ�����W�҂͈̔͂̊g��ƁA�Z�p�I�E���x�I�ȑO��̈Ⴂ���������邽�߂ł���B
�܂��W�҂͈̔͂̊g��ɂ��ẮA�����܂������Ƃɂ�肻�͈͎̔͂��ދƎҁA�����ƎҁA�����Ǝ҂����łȂ��A��s�A�ی���ЁA������ЁA����ɂ͒ʊƎҁA�ŊցA���̑��֘A�Ȓ����ɂ܂Ŋg�傷��B����́A���u�n����ł��邽�߂ɁA�ݕ��̈��n����������̕��@�ō�������ƈقȂ�葱���̗p���Ă��邱�Ƃ�A�������z�������ł��邽�߂ɁA���ʂ̗A�o�����x���[���ւ���Ă��邽�߂ł���B
�܂��ASCM�\�z�ɂ������Ă͎���̂��߂ɏ��̋��L���K�{�ƂȂ邪�A���̂��߂̋Z�p�I�E���x�I�O��v���Ȃ��ꍇ�������B��ƌX�̏�̓x���������łȂ��A�������Ƃ肷�邽�߂̋Z�p�I�Ȏ�茈�߂�A���̍ۂ̃��[���Ȃǂ���v���Ă��Ȃ���A�����܂����������̋��L�͎����ł��Ȃ��B
���̂悤�Ȕw�i����AGSCM�͍��������SCM�Ɣ�r���Ă��̎������͂邩�ɓ���A�����_�ł͌������܂߂Ď���͋ɂ߂ď��Ȃ��B
������
SCM���i��̉ۑ�������͌����E��̉����ׂ����ڂ������BSCM���i�𐬌��ɓ����ɂ́A���̖ړI��c������ƂƂ��ɁA����ɑΉ����錟���ۑ�ւ̑Ή������̉����Ă����K�v������B
�V�X�e���\�z�i�\�t�g�E�F�A�����j�ɂ������Ă��A�ۑ�⌤�����ׂ��e�[�}���\���ɔF�����Ă������Ƃ���ł���B

|
�@�O���[�o�����ɂǂ��Ή����ׂ���
�P�D�͂��߂Ɂi�O���[�o�����Ƃ́j
�@�����ł́u���ۉ��v�Ɓu�O���[�o�����v�`�Ƃ���B�ȉ��u�O���[�o�����v����Ƃ��Ďg�p����B�܂��O���[�o�������i�Љ���A�O���[�o���Љ�ƌĂԂ��ƂƂ���B
�@�u�O���[�o�����v�Ƃ́A�l�E���E���Ȃǂ��A�������z���Ď��R�ɍs�������邱�Ƃł���B���̍s�����ł���x�������O���[�o���x�ƌĂсA�ΊO�J���x�ƑΓ��J���x�ő��肳��Ă���B�����ł͓��{�͑�����28�ʂƂȂ��Ă���A���Ȃ�̏o�x�ꂪ������B
�@��ƌo�c�ɑ傫�ȉe����^����o�ςɂ��Č����A���E�o�ς��K���̖������R�ȋ��������ň�F�ɓh��Ԃ����\�}�Ƃ������Ƃ�������B�܂�A�O���[�o�����͒P���Ƀr�W�l�X�ɍ����͖����Ƃ����Ӗ��ŁA�����ȃn���O���[�ȑ���Ƌ������邱�ƂƑ�����̂������I�ł���B
�@�O���[�o�����̔��z�́AICT�ɂ��C���X�^���g�ȃO���[�o�����[�`���\�ɂȂ�A�u���ɏ���E���Ɋg�U���邱�ƁA����ѐ��E������������W���邱�Ƃɂ��A���̋��E�Ƃ����ӎ������ꂽ���Ƃ��琶�܂ꂽ�ƍl������B
�@�Q�D�O���[�o�����̌��Ɖe
�@�O���[�o�����͍����̕ǂ������Ȃ邩�A�Ⴍ�Ȃ邱�ƂƑ�������B���̂��Ƃ́m��肭�������n���E�K�͂ł̃r�W�l�X�`�����X�̊g�傪���҂ł���Ƃ������Ƃł���A���̕����ƌ��邱�Ƃ��ł���B
�@���������ۂ́A���R�Ɨ����͂�����ǂ𗘗p���Ď��R�Ȏ��{�ړ��𑀍삵�A����ȗ��v���グ�₷������\���ɂȂ��Ă���A�n����������x�߂鍑�ւ̎��{�ړ��ɂ��Ă̂ݍ����������B����͐Z�����̂悤�Ȃ��̂ŁA�����t����Z������ʂ��ĔZ���t�̕����ɗ��ꍞ�ލ\�}�Ɏ��Ă���B
�@�O���[�o��������ł��傫�ȗ��v�������o�����Ƃ����H�����̂��č��ł���A���̂��߂̓���ƒm�b�𑁂����珊�������B�����ŃO���[�o�����Ƃ͐��E�̕č����ł���A���ꂪ�i�W���Ă���ȏ�A�R�̂��߂ɂ͓����y�U�ɏオ�炴��Ȃ��Ƃ̂��߂��������o�Ă���B
�@���������͎�����H�̐��E�ł���A�O���[�o�����̉e�̕����͍����Ƃ́A�܂����ꍑ���ɂ����Ă��n�x�̍��̊g��ł���B90�N��㔼�̃A�W�A��@�Ɍ�����悤�ɁA�����̍��̌o�ςƊ�Ƃ̔j�]���������Ƃ�����B
�@����ł͎��{��`(���R)�o�ς��Љ��`(�v��)�o�ς��A�����̌o�σV�X�e���ł͉e�̕����ւ͑Ή�������Ă��Ȃ��B�o�ς���邽�߂ɂ͋K���ɂ�鎩���D�ʂ̕ǂ�z�����Ƃ��őP��ł���Ƃ����������A���Ȃ����ے�͂ł��Ȃ��B���̂悤�ȏł́A�e���̘A�g�ɂ��s���w�j�̏��炪�K�v�ƂȂ�A���̎������グ�邽�߂ɂ�����ǖʂŊ�Ƃ̉ʂ����������傫���Ȃ��Ă���B
�@�O���[�o���Љ�ɂ������ƍs���́A���v�Nj��^����E�炵�O���[�o���K�͂ł̐V���ȖڕW��]���ړx�������Ƃ����߂��Ă���B�ꍑ�P�ʂł̋����l�����ł͂Ȃ��A���E����Ƃ����傫�Ȍo�c���O�������Ƃ��K�v�Ƃ���Ă���B���̂悤�ȍl�����̊�ՂƂ��Đ���������Ă���̂��u�����E���n�̗��O�v�ł���B
�@
�@�R�D�����E���n�̗��O���ǂ������邩
�@������H�Ƌ����E���n�Ƃ͑��e��Ȃ��B�Љ�̐��n�A�s��̖O�a�ɂ�ď]���̉ߓ������ł͍s���l�܂肪�����A���������ł͂��̏�Ŕj���邱�Ƃ͓���Ȃ��Ă���B�[���T���Љ�ł͂Ȃ��A����ꂽ�p�C���������Ƃ��A���ꂩ��̎Љ�p�����邽�߂̑Ή���ƂȂ�B
�@�����E���n�Ƃ́u���ɐ������W���邽�߂ɁA�����I�Ȓ����ɂ����đΓ��̗���ŋ������Ă������Ɓv�ƒ�`�����B�܂�A�I�[�v���ŃN���A�Ȏs��ɂ����āA�e���̊�Ƃ����݂��̉��l�ς�F�ߍ����A���Ƃ⑊�݊W��ʂ��ĊW�҂̑��Ă����v��������ݏo�����Ƃł���A��Ƃ���������芪�����Q�W�҂�e���̌o�ώЉ�ɔz�����A�ϗ������炵�����ȋ����ɓO����Ƃ������Ƃł���B
�@�u�����E���n�̗��O�v���o�c�ʂő�����Ƃ��A�e��Ƃ��n���V�X�e���̈���ł��邱�Ƃ�F�����A�����͂�ˑ����������̌`���ɓw�͂��邱�Ƃ��K�v�ł���B���̂��Ƃ�ʂ��āA�O���[�o���o�ς̒��Ŋm�ł���n�ʂ��m�����A���l��i�܂莩��̕K�v����j�����������A���̑��݈Ӌ`��ۂ������邱�Ƃ��o����̂ł��낤�B
�@
�@�S�D�O���[�o�����ւ̑Ή�
�@�O���[�o�����͂��͂�I�����̈�ł͂Ȃ��B�������ƂɂƂ��āA�ً}��v����K�{�̐헪�ł���B�O���[�o����ƂƂȂ�K�v�����͐��E���̎s��ɐi�o���邱�Ƃł��邪�A���ꂾ���ł͏\���ł͂Ȃ��B�����ɂ͋@����łȂ����Ђ����݂���B�v���������Ȃ��Ƃ��납��ˑR���G���o�����āA�Q���݂��P���邱�Ƃ�����B�ꍑ�s��ł�����哱�͂��������Ƃ��Ă��A���ꂾ���ł̓O���[�o���s��̃��[�_�[�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�@�O���[�o����ƂɂȂ邽�߂̗v���Ƃ��ẮA�傫����̐���ő����邱�Ƃ��ł���B��͋����D�ʐ��̖ʁi�����ɑ���D�ʐ��̕ێ��j�A������͋����E���n��(�i�o��̐M���̊l��)�ł���B����������ɍ��������Ƃ��ɃO���[�o����ƂƂ��ĔF�߂��邱�ƂɂȂ�ƍl����B
�@�S�D�P�@�����D�ʐ��̖�
�@�I�y���[�V�����ʂł̌������ɍ��������D�ʐ��̊m���ł���A�T�v���C�E�`�F�[���̃O���[�o�����A���{�̃O���[�o�����Ȃǂ�����B
�@�T�v���C�E�`�F�[���̃O���[�o�����Ƃ́A�����j�[�Y�ɉ����邽�߂ɁA���E�I����ɂ����čł����_�̂���n��ɃA�N�Z�X���邱�ƁA�܂�œK�s��A�œK�n�w���A�œK�n���Y���w�����邱�Ƃł���B���{�x�[�X�̃O���[�o�����Ƃ́A���E�I����ɂ����� �œK�Ȏ��{��������ѓ����`�Ԃ�I�Ԃ��Ƃł���B
�@����܂ł́A�e��ƂƂ��R�X�g�_�E�����������ɖ�N�ƂȂ��Ă���A���̖ʂł̋����͌���ɂ̂ݖڂ������Ă����B����́u�����E���n�̖ʁv�ɂ��������ڂ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�S�D�Q�@�����E���n�̖�
�@�s��ł̑��݈Ӌ`�̊m���ł���A��Ƃ̍l����(��ƕ��y)�̃O���[�o���������S�ƂȂ�B�e���ɂ����镶������Ȃǂ̑��l������Ƃ��������A��������ꂽ�Ƃ��ɂ܂������{���̃O���[�o����ƂɂȂ����Ƃ�����B���̂��߂ɍ������ׂ���̓I�ۑ�Ƃ��ẮA�@�ٕ��r���̎v�z�A�A���I�ȕ��y�i���{�͓��ꂾ�Ƃ����v�����݁j�A�B���ԓ����{��`�Ȃǂ��グ����B
�@�ˑR�ɋ������肩��Q���݂��P����\�������邩��Ƃ����āA������o�������Ƃ����i�̂Ȃ��s���͊��S�ł��Ȃ��B��Ƃɂ͕i���A�C���e�O���e�B�A�������߂���B�����ɗ��r�����s����ςݏd�˂邱�ƂŐM���������A�����E���n�̓y�䂪�o���オ��B�O���[�o���Љ�Ő����邽�߂ɂ́A���̂悤�Ȋ�ƕ��y�̌`���ƂƂ��ɁA�ȉ��̔F���y�E�Z��������K�v������B
�@�P�j�i�o��̌��n�s��́A�����Ƃ͈قȂ��Ă��邱�Ƃ𗝉�����B
�@���ɂ���āA����A�J���`���[�͂����܂ł��Ȃ��A���������A�ڋq�̚n�D�A���ʃV�X�e���Ȃǂ��傢�ɈقȂ��Ă��邱�Ƃ�z�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�Q�j���n�ւ̋Z�p�E�m���ړ]�����s����B
�@�d�v�Ȏd���͌��n�X�^�b�t�ɔC���Č��n������Ƃ���������Ƃ�A���n�ł̉ۑ�͌��n�ʼn�������Ƃ������^�c�Ɉڍs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�R�j��Ɨϗ����m������B
�@�ׂ��邽�߂ɂ͉������Ă��ǂ��Ƃ�����ł͂Ȃ��B���튈���̋��菊�ƂȂ�ׂ�����m�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����̓g���u�������������ۂɓ��ɗL���ɍ�p����B
�@
�@�T�D������
�@�{�R�����ł́A�O���[�o�����ւ̑Ή��Ƃ��ċ����E���n�̗��O���d��������Ɗ����W�J�̏d�v����_�����B�����̂��߂ɂ̓O���[�o���ȍl�����i�O���[�o���}�C���h�Z�b�g�j�̍\�z���d�v�ł���B
�@��������H����̂́u�l�v�ł���A�l�̈琬���K�v�ƂȂ�B��Ƃ̓O���[�o���}�C���h�Z�b�g�̋����W�J����ƂƂ��ɁA�O���[�o���l�ނ̈琬�ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

|
�@���X������
�͂��߂�
�@�l����Ƃ����X���]�����Ƃ����C�����ŕ\�����܂����B�u�����v�͑�w���ɂ�����܂����A�u�������̌��킴��ǂ����������𐬂��s�u�j�L�v���L�`�^����t�v�Ƃ���悤�ɁA�u���������◛�̖̉��ɂ́A�l�����Ď��R�ɘH���ł���悤�ɁA���̂���l�̎���ɂ͎��R�Ɛl���W�܂��ď]���悤�ɂȂ�v�Ƃ����Ӗ��ł��B
�@����܂Ōo�ώЉ�̃L�[���[�h�́u�����v�ł����B�������E���オ��̐������ł̊����͂��͂�藧���܂���B�ʂ�莿�����߂邱�Ƃ����߂���悤�ɂȂ�܂����B�������߂鐬���́u���n�v�Ƃ����\��������܂����A�����ł͎Љ�ɔF�߂���Ӗ������߂āu�����v�ƕ\���Ă݂܂����B
�@�ł͊�Ƃ����߂�ׂ����Ƃ͉��ł��傤���B���̃q���g�Ƃ��Čo�c��̏d�_�ۑ�ɂ��Ă̒���������܂��B����ɂ��ƍ����ʂ̋����ȂǎГ��̓����̐����ł߂���ŁA�u�V����i�o�E�V���ƓW�J�v�ȂǍU�߂̌o�c����������X�����݂��܂��B����Ɂu�r�W�����E�헪�v�A�u��ƊԘA�g�v�A�u�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�v�ȂǁA��Ƃ̂�������o�c��̏d�v�ۑ�ƂȂ��Ă��܂��B���̊�Ƃ̂�����ɂ��čl���Ă݂܂��B
�r�W�����E�헪
�@�Ȃł����W���p���̊��܂��]���Ɏc���Ă��܂��B�u���W�����[���h�J�b�v�o��Ɍ����ĕ��킵�Ă���j�q�T�b�J�[���y���݂ł��B�Ȃł����L���v�e���̑�I��́u���͌�����̂ł͂Ȃ���������́v�A�����āu���q�T�b�J�[�ɖڂ������Ă��炤���߂ɗD������v�Ƃ����v���ŁA��\�ɂȂ��Ă���10���N�Ƃ��������ɓn��w�͂𑱂����܂����B
�@�����āA���[���h�J�b�v�ł̗D���ƃI�����s�b�N�ł̏��D������X�Ɍ��C�Ɨ͂�^���Ă���܂����B����͗D����������Ƃ��������łȂ��A�����Ē��߂Ȃ��A�|����Ă����������オ��A�����s�ׂ͂��Ȃ��Ƃ����A�Ђ������Ȏp�����������Ă��炾�Ǝv���܂��B
�@�T�b�J�[�Ƃ����A�ē��ւ�����Ƃ���ɗD���𑈂��`�[���ɕϐg������A�R�̂悤�ɂЎ�ɂȂ�P�[�X���U������܂��B�v���C����̂͑I��ł����A�ē̑��݂����ʂɑ傫�ȉe����^���邱�Ƃ����Ď��܂��B
�@�܂��A�r�W�����������Ƃ������Ƃł��B�D���Ƃ����X�g���b�`�����ڕW���������Ƃœ��@�Â����Ȃ���܂��B�����ď����߂̐헪�i�T�b�J�[�ł̓V�X�e���j����̉����邱�Ƃł��B�����ɏ����߂ɂ͓��_���K�v�ł����A�S�����_������킯�ł͂���܂���B���_�������̂��������ڂ𗁂т�̂ł͂Ȃ��A�����o�[�S�Ă��B�����𖡂킦��悤�ȁA���m�Ȗ������S��g�D��肪���߂��܂��B
�@����ɑ傫���֗^����̂̓`�[�����ł̋��ʔF���Ƒ��ݗ����ł��B���[�_�[�V�b�v�����邽�߂ɕs���Ȃ̂̓R�~���j�P�[�V�����̉~�����ł��B���[�_�[�̎w��������Ƃ���Ӗ����������Ă��Ă͕����͐i�݂܂���B�u�o�x���̓��͂Ȃ����s�������v�Ƃ����₢�����ɑ��āA���鎞�܂Ől�ނ̌��t�͈�ł��������A�o�x���̓����\�z���Đ_�ɋ߂Â����Ƃ����l�ނ̖�]�ɐ_�����{���āA�l�X�̌��t�𑽂��̈�������t�ɕ��������߂ɁA�R�~���j�P�[�V��������ꂸ�Ɍ��ǎ��s�����Ƃ�����������܂��B
�@�������t��b���Ă��Ă������������Ă��Ȃ��P�[�X�́A�X�|�[�c�ɂ����Ă��r�W�l�X�ɂ����Ă��A�܂��������ɂ����Ă������ɉɂ�����܂���B�������Č���ƁA�ēƌo�c�҂̓��[�_�[�Ƃ��āA���̎�r�͗ގ����Ă���Ƃ����Ă��ǂ��ł��傤�B
��ƊԘA�g
�@M&A��o�c���������ڂ���Ă��܂����A�����ł͘A�g�ɂ���Ɖ��l�̌���ɂ��čl���܂��B�A�g�͊�ƊԂ݂̂łȂ��A�n��E�Љ�Ƃ̘A�g���܂݂܂��B
�@�Љ�Ɏ������̂͂ǂ̂悤�Ȋ�Ƃ��ɂ��āA�V�����l�����≿�l�ς������ďn������K�v���ɉ����āA�s��Ɏ�����鏤�i�͂����Ȃ���̂����������������邱�Ƃ���ł��B��ƂɂƂ��ẮA�܂��܂����l�Ȏ��Ƌ@��������܂��B�h���b�K�|�̂����u��������}������A�V�����@��ɒ��ڂ��đn������v�����H���ׂ��ł��B���ׂĂ̋@��ƃ`�����X�͊O�ɂ���̂ł��B
�@���������V���ȋ@���I�m�ɑ����邽�߂ɂ́A���ʉ����ꂽ�����Z�p���x���ƃ\�t�g�E�T�[�r�X�ʂł̋����̑��ɁA�t���L�V�u���Ȏ��Ɖ^�c�Ƃ�����\�Ƃ���_��ȑg�D�`�Ԃ̍\�z���K�v�ƂȂ�܂��B�����āA�X�̊�Ƃɂ����鋭�݂��������A��݂��������邽�߂ɘA�g�͕K�{�Ƃ�������ł��傤�B
�@���ɂ����Ă��A����17�N4��13���Ɏ{�s���ꂽ�u������ƐV���Ɗ������i�@�v�Łu�V�A�g�v���A����20�N7��21���Ɏ{�s���ꂽ�u������Ǝ҂Ɣ_�ы��Ǝ҂Ƃ̘A�g�ɂ�鎖�Ɗ����̑��i�Ɋւ���@���v�Łu�_���H�A�g�v�̐��i���㉟�����Ă��܂��B�܂��A����19�N6��29���Ɏ{�s���ꂽ�u������Ƃɂ��n��Y�Ǝ��������p�������Ɗ����̑��i�Ɋւ���@���v�ł́A�ʊ�Ƃł́u�n��Y�Ǝ������p���Ɓv���㉟�����Ă��܂����A����͊�Ƃƒn��Ƃ̘A�g�ƌ��邱�Ƃ��ł��܂��B�����̘A�g���Ƃɂ��Ў��g��ł������������Ǝv���܂��B
�@���̂悤�ȘA�g�ւ̎��g�݂ɂ��A��Ƃ��U�������݂̂łȂ��A�n��o�ς̊��������}���A�ߍ]���l�̏��Ɨ��O�ɂ���u�����悵�A������悵�A���Ԃ悵�v�Ƃ����u�O���悵�v�Ƃ������t�̎��H�ƂȂ�܂��B����Ɉ���i��œ�{�����̂��������i�x�̊Ҍ��j�ɂȂ���܂��B
�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X
�@��Ƃ͎Љ�ɔF�߂��Ă����p�����܂��B�����ĔF�߂��邽�߂ɂ͕]������悤�ȍs�������s���Ȃ���Ȃ�܂���B�ł͕]������悤�ȍs���Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��傤���B����́A�����Ƀr�W�l�X���s�Ȃ��Љ�̈ێ��E���W�Ɋ�^���邱�ƁA���̍s���������ł���悤�ɑg�D�̗����ƗǐS�������d�g�݁i�̐��A���x�A���y�j������邱�ƁA�ł���Ƃ�����ł��傤�B
�@�O�҂͊�Ƃ̌o�c���O���K�肷����̂ł��B�w����������Ƃ͉��̂��߂ɂ���̂��x�Ƃ��������I�Ȗ₢�ɓ�������r�W��������щ��l��������K�v������܂��B�܂���҂͂��̕����֎�����Ă����A�K�v�ɉ����Č��������ł���\�͂�\���Ă��܂��B�o�c���O�Ɋ�Â��ăC���e�O���e�B���A��V��������Ɗ��������s�����悤�Ȏd�g�`�����邱�Ƃ��K�v�ł��B
�@��Ɨϗ��͌o�c�ɂ����鐽�����̔����Ƃ����A����Ύ���I�Ȋ����ł͂���܂����A���g��ł����g�܂Ȃ��Ă��ǂ��Ƃ������̂ł͂���܂���B�ŏ����͈̔͂̓������K�肵�Ă�����̂��@���ł���A����ȏ�͈̔͂��K�肷����̂��ϗ��Ƃ��錩�����L�܂��Ă���A��Ɨϗ��̓����O�ꂽ�ꍇ�͖@���I�Ȕ����͂���܂��A��Ƃ̑������낤������قǂ̎Љ�I�����i�M�����āA���i�{�C�R�b�g�A�]�ƈ��̃����[���ቺ�Ȃǁj�����̂ł��B�t�ɂ����A�Љ�犴�ӂ⑸�h������Ɗ��������s���邱�Ƃ��A�ɉh�ւ̕K�v�����ł�����܂��B
�@�ϗ��ψ���s���Ƃ́A������������Ė�肪����Ύ�̓I�ɂ�������߂�B�������A�g�D�ɂ����Ă͖�E�̏㉺�̕ʂȂ�������s�Ȃ��B���̂��߂ɁA����������ԓx�A�傫�ȗ���ɖ��ᔻ�ɓ������Ȃ��ԓx�A��肪����ꍇ�͂��������ԓx���������̂ł��B���ꂪ�{���ł���ƍl���܂��B
������
�@�ȏ�̂悤�Ȏ������߂銈�����p�����邱�ƂŁA�Љ�ɋ��߂����ƂƂȂ���̂ƍl���܂��B�u���{�ň�ԑ�ɂ�������Ё@���̂P�A���̂Q�A���̂R�v�i��{���i���A�����o�Łj�ɂ́A���̂悤�Ȋ�Ƃ��Љ��Ă��܂��B���҂͖@����w��w�@�����Łu����Œ�����ƌ����₪��钆����Ƃ��x������v���Ƃ����b�g�[�ɁA6000�Ђ����Ƃ�K�₳��Ă���Ƃ̂��ƁB���̑����̑�ɂ�������Ђ̒�����i���ďЉ��Ă��܂��B
�@�w��Ђ͒N�̂��߂Ɂx���l����Ƃ��A���q�l�A����A�����A�n��Љ�A�]�ƈ��Ȃǂ̑����̃X�e�[�N�z���_�[���グ���܂����A���҂͍ŏ��ɂ�����ׂ��͏]�ƈ��ł���Ǝ咣����Ă��܂��B��Ђ̎g���͌o�c���O��r�W�����ɂ��\������Ă���A���̎����͏]�ƈ��̍s���ɂ��Ȃ���A�ނ炪���������Ɗ������Ȃ���ΒB���͏o���Ȃ��Ƃ����̂����̗��R�ł��B�]�ƈ������x�̏d�v�����グ���Ƃ������Ă��܂����B
�@�ŏI�I�ɂ͑I��̓������傫�����̂������܂��B�������̂Ђ������ȃv���C�A�����Ă�����߂Ȃ��S�E�E�A��Ƃɂ����Ă������o�[�̊��������Ƃ����s����ʂ��āA��Ɖ��l���傫�����シ��ł��傤�B
�@���̂悤�ȍs�������߂̊�����邱�ƁA�����ĎЉ�ɖ𗧂悤�Ȍo�c�𑱂��邱�ƁA�������g�D�^�c���s�����ƂƂ������A����Γ�����O�ł����{���I�ł��D�����̂��ӂ����g�݂̑�����A�����͖]�߂��������ɔ敾�����Љ�ł�����x�U��Ԃ�ׂ��Ɖ��߂Ċ����Ă��܂��B